インボイス登録、本当に「任意」でしたか?
2023年から始まったインボイス制度。 「登録は任意」とは言われつつも、私と同じように、クライアントから実質的に登録を促され、悩んだ末に登録したCADオペレーター仲間も多いのではないでしょうか。
私も、2つの事業の元請け、両方から登録を促されました。 「登録しなければ、その分の報酬が下がってしまう」 ——これは、任意とは名ばかりの、事実上の「強制」でした。
この記事では、華々しい節税術ではなく、私のような副業者が直面したインボイン登録の“リアル”と、その先にある「手取りが減っていく恐怖」に、どう立ち向かおうとしているのか、その戦略についてお話しします。
なぜ、「交渉」はいつも“他人”軸の戦いなのか
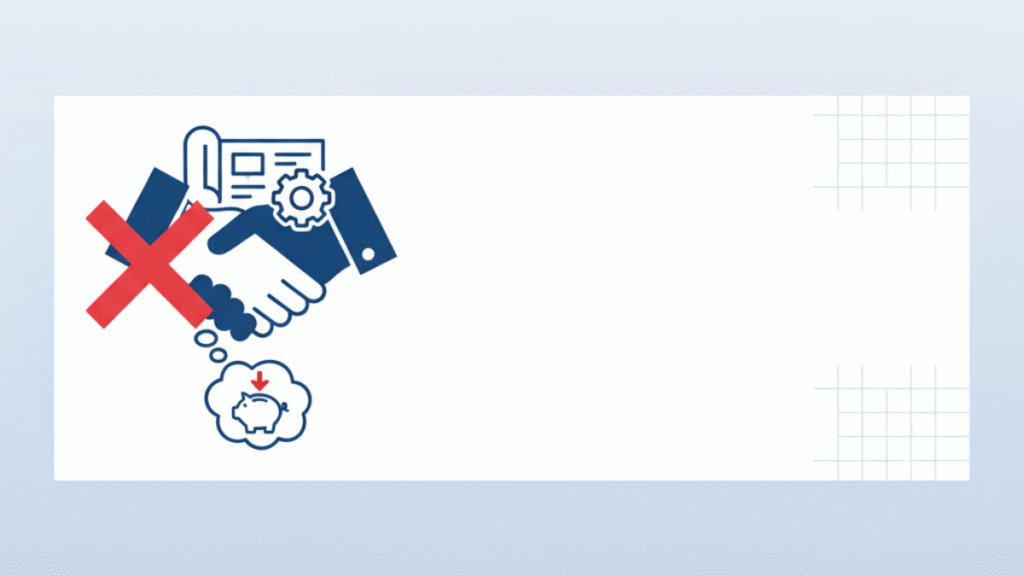
このインボイスの問題は、私が以前から直面している「単価交渉」の問題と、全く同じ構造をしています。
私は以前、クライアントの「構造的な事情(=設計担当者のインセンティブから作図費が引かれる仕組み)」によって、単価交渉に失敗した経験があります。 この経験から学んだのは、クライアントの事情(=他人の領域)は、私にはコントロールできないという現実でした。
今回のインボイスも同じです。 当時、「インボイス登録しなくても、“選ばれる人”になればいい」という意見も多く見かけました。しかし、それは実質、「単価交渉ができる人(=クライアントから単価UPしてもらえる人)」という意味です。
私のように、クライアントの構造上、単価交渉が難しい人間にとっては、それもまた“他人”軸の戦いであり、現実的な解決策ではありませんでした。 結局、「国の制度(=さらに大きな他人の領域)」によって、私の意思とは関係なく、手取りが減ることが決まってしまったのです。
「2割特例」という“一時しのぎ”と、その先の“恐怖”

クライアントとの関係上、インボイス登録(課税事業者になること)を選んだ私ですが、もちろん、納税の負担を少しでも軽くするための「2割特例」を活用しています。
【簡単解説】2割特例とは? インボイス登録にあたって、新たに消費税を納めることになった事業者(※条件あり)のための、期間限定の“激変緩和措置”です。 難しい計算は抜きにして、「売上(税抜) × 10% × 20% = 納める消費税」、つまり、売上にかかる消費税のうち、2割だけ納めればOKという、非常にお得な制度です。(※2026年9月30日の属する課税期間まで)
この特例のおかげで、数年間は納税の負担がかなり軽減されています。 しかし、私が本当に感じているのは、「この特例期間が過ぎたら、どうなるのか?」という、将来へのリアルな“恐怖”です。
特例が切れた瞬間、問答無用で、私の手取りは今よりもさらに減る。 (※編集注:2割特例終了後は、売上によっては「簡易課税」などの別の制度に移行できますが、多くの場合、2割特例よりは負担が増えます)
その「Xデー」は、もう決まっているのです。
【まとめ】“他人”が作るルールに、どう立ち向かうか?
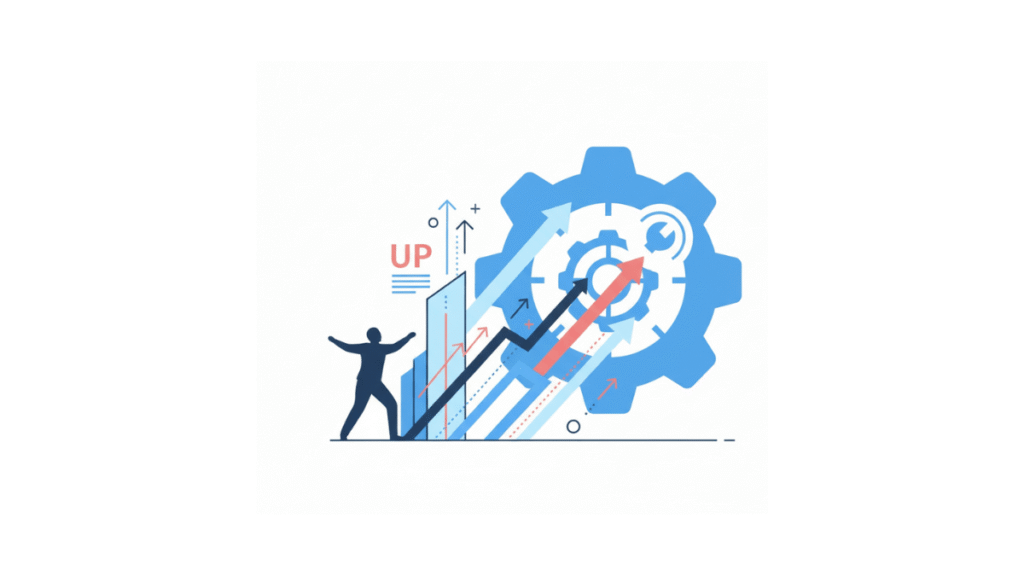
「単価」も「税制」も、私にはコントロールできません。 “他人”が作ったルールの中で、私たちは生きていくしかない。
では、指をくわえて、手取りが減るのを待つだけなのでしょうか? いいえ、違います。
私が「単価交渉」に失敗した時に気づいた、あの“唯一の道”を、今こそ進む時です。
「相手(単価や制度)を変えられないのなら、自分(作業スピード)を変えるしかない」
特例が切れて手取りが減るなら、それ以上に「作業時間を短縮」し、「時給を上げる」ことで、その損失をカバーする。 それこそが、私たち“クリエイティブじゃない”人間が、この先生きのこるための、最も現実的で、確実な“生存戦略”です。
だからこそ、私は今日も「効率化」を極め続けます。



コメント